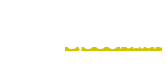【ブログ・佐々木千鶴】舞台の上では分からなかった「死」と出会って

こんにちは。マキノ祭典葬祭部の佐々木千鶴です。
宮城県の田舎町で育ち、高校・大学と演劇に夢中になってきました。
脚本を書いて、舞台に立って、時には殺陣で斬って、斬られて……そんな私が今は葬儀の現場にいます。
「ずいぶん方向転換したね」と言われることもありますが、私の中では、どこかつながっている感覚があります。
脚本では何度も「死」を描いてきました。でも本当のお別れの場には、ことばにしきれない想いがあふれています。
今回は、そんな私が日々見つめている「現実の死」と、そこに寄り添うお仕事のことを、少しだけお話ししようと思います。
故郷・宮城で出会う舞台芸術の世界
私が生まれ育ったのは宮城県大崎市。仙台から北に車で約1時間ほど走った、自然豊かな田舎町です。
中高一貫校に通っていた私は、中学では吹奏楽部でクラリネットを吹き、その一方で、芸能や演劇への興味もずっと持ち続けていました。
中学3年生の時に、高校からしか入れないはずの「吟詠剣詩舞」愛好会に飛び入りで参加させてもらうことに。そして、高校では念願の演劇部にも入部。伝統芸能と現代劇の両面から、舞台芸術の世界にどっぷり浸かります。
吟詠剣詩舞というのは、詩吟と舞を組み合わせた、平安時代から続く芸道のことです。吟者が詩や和歌をうたい、それにあわせて舞者が刀や扇を手に、詩の情緒を舞で表現します。和の美しさが凝縮された、本当にかっこいい伝統芸能なのです。
一方で、演劇部では数々の現代劇を手がけました。役者、大道具、脚本、演出まで、すべてを自分たちでつくりあげていく中で、特に私は、自ら物語を生み出すことのできる脚本にどんどん惹かれていきます。
「脚本をもっと極めたい!」
そんな思いを胸に上京。大学では演劇学科を専攻し、脚本制作を学びます。
また、学内の殺陣サークルにも参加して、高校時代と同じように、伝統劇と現代劇の両方に打ち込みました。
芸術は死を語るためのもの
芸術って、なにのためにあるんだろう。そう考えた時に私の中で浮かぶのは、
「芸術は死を語るためにあるのでは?」
…ということです。
たとえば、高校3年間で取り組んだ吟詠剣詩舞の演目には、たくさんのテーマがあります。
刀をもつ「剣舞」では、武士道や忠義、国を想う気持ちがよくうたわれますし、扇を持つ「詩舞」では、四季のうつろいや自然への賛美、恋や別れ、無常といった、繊細な心の動きが表現されます。
なかでも、死をテーマにしたものは観る者の胸を打ちます。
吟詠剣詩舞では、死を「こわいもの」や「かなしいもの」としてだけでなく、その奥で、「潔さ」「覚悟」「美学」のようなものとして語ることが多いのです。
たとえば『白虎隊』。少年たちが自ら命を絶つという、日本人ならだれもが知る歴史的な悲劇ですが、ここにも、悲哀の中に「若さ」や「無常観」というテーマが込められています。
伝統芸能だけでなく、映画でも、ドラマでも、まんがでも、アニメでも、いたるところで人が死ぬ姿が描かれます。病気にかかり、天災に見舞われ、戦争におそわれ、色恋沙汰にまき込まれ、いろんな人が、いろんな形で死んでいく。
もしかしたら人間はずっと、「たった一度きりしか体験できない死」というものを、物語や芸術を通して追体験しようとしてきたのではないでしょうか。
殺陣の稽古でも、私はたくさんの人を斬り、そしてたくさんの人に斬られてきました。
数を重ねることで、「自然な斬り方」「美しい倒れ方」がうまくなり、師匠や先輩にほめられると、素直によろこんだものです。
人を斬るまね、人に殺されるまねを、職人技にまで突き詰める人間って、本当におかしな生き物だと思います。でもそれこそ、人間が「死を理解したい」「再現したい」と願っている証なのかもしれません。
たった一度しか経験できない「死」というものを、せめて、物語や芸術の中で追体験しようとする。そういう人間の祈りにも似た営みが、芸術には込められているのだと思います。
別れの瞬間をまのあたりにする日々
マキノ祭典での日々は、これまでとはまったく違う「現実の死」と向き合う時間です。そしてそのたびに、私はいつも「ことばにならない想い」と出会います。
脚本を書く身としては、本来「ことばにならない」はご法度のはずなのですが、葬儀の現場で出会うご遺族の想いは、そう簡単に言語化できるものではありません。
故人さまお一人おひとりに、語り尽くせない人生があります。歴史に名を刻むような人物でなくとも、その方にはその方だけの物語があり、その方を大切に想う人がいて、たしかに愛された記憶があります。
詩吟でたたえられるような英雄ではなくても、家族のなかでは、かけがえのない存在だったということ。そうした日常の尊さにふれるたび、私は胸がいっぱいになります。
脚本や小説の中では、死はしばしば劇的に描かれます。ですが、実際の死は時に静かで、平凡で、また時に複雑で、劇的だったりもします。
葬儀の仕事に就いてみて知りました。芸術で語られることのない死が、この世界には無数にあるのだということを。
そして当人たちにとっては、歴史に残る名作よりも、目の前にいる人と紡いできた物語の方が、はるかに価値があるということを。
私はこれまで、役者として書き手として、たくさんの物語を創作してきました。でも、葬儀社の仕事では、お客様の声を「聴く」ことに徹しています。
これまでずっと、物語を創ることに夢中だった私が、今はお客様の物語に耳を傾ける日々を過ごしている、そのことをとてもありがたく感じています。
「お父さんは、毎晩晩酌のビールを楽しみにしていたのよ」
「家族みんなで行った沖縄旅行が忘れられないね」
歴史に残ることのない、このようなささやかな、でも亡き人やご家族にとってはかけがえのない物語こそを、私は大切にしていきたいと思います。
そしていつか、これらのささやかな物語の一つひとつが、私自身の表現として結実し、これまで出会ったすべての方々への小さな捧げものになれば、これほど嬉しいことはありません。